殺風景な高層ビルのベランダに、青い朝顔が眼下の街を見渡すように伸びている。私が「朝顔などあればいいと思うのだが、どうだろう」 と、気まぐれに言ったことを真に受けたのか、いいや、そうではあるまい。おそらく気まぐれに鉢だの土だの種だのを購って、栽培を始めてしまう花子はとても愛らしい。
目覚めたばかりの、汗の残る体と髪とを、洗い流した冷たい水は朝露にも似ている。毛先から滴り落ちる粒の一つ一つを集めれば、小さな海とは言わずとも、水溜りくらいはできるだろうか。その水溜りを掌に握ってみたら、どんな心持がするだろうか。その小さな世界の中で、私はいつまでもおぼれてしまいたい。
「こどものころを思い出す」と言って、生乾きの髪をそのままに、みずみずしさ残る指先が鮮やかな緑の葉を乱暴に撫でまわす。その傍若無人な振る舞いは、見ていてとても心地がよい。花子はしたたかであり、一方で頼りなげな腕の細さは、しかし見たままの脆さを物語っていた。
まるで遠慮のない夏の日射が彼女の柔肌を蹂躙する。それすら構うことなく濃緑の中へ腕を突き刺し、鼻を近づけ、生々しい生命力を互いに受け渡している。
私は彼女の、こどものような無邪気さが、海のような深みが、私を生かしてくれているのだと信じている。花子の生命力を分け与えられて、この体は動き、このこころは動く。
花子を抱きしめてみたのなら、どんな心持がするだろうか。
さしずめ透明なひかりの束を抱えるような、あるいは甘い水を掬い上げるような、そんな心持になれるだろうか。それとも冷たい氷となって、嘘偽りの私のいのちを拒むだろうか。
「一年っきりで枯れちゃうなんてもったいないねえ」
朝顔を惜しみ、花子は額の汗を拭う。溶け出した氷のようだ。氷山は崩れ、大海と溶けあい、露と消えるだろう。肌は潮のかおりがするだろう、あまみすら感じられるであろう。
「ねぇ、拓海?」
私は、まるでひらがなのようにまろやかな響きで私を呼んでくれる、舌足らずな彼女を愛していたい。
朝顔に紛れて波間に揺れる、彼女を腕に抱きしめていたい。
夏のあなたは美しい。
日が昇るころ、朝顔と海とを愛でるあなたのまなざしが美しい。果てどのない水平線の向こうに何があるだろうかと、私に尋ねるあなたの声はまるで鈴のようだ。私はその凛とした音を、飽くことなく聞き続けたい。
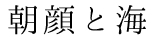
草加 拓海|ジパング
