何時だろうか。目を覚ましたときにはまだ雨が降っていた。昼寝のせいで熱を孕んだ肉体のけだるさと、自分以外の呼吸をこの腕に抱えたまま、吹き飛ばされた記憶を呼び戻そうとする。いつの間に眠っていたのか覚えてはいないが、腕の中でいまだ眠っている花子の頭の横に放り出された本の背表紙には覚えがあった。
ああ、とすべてを思い出して、もう一度怠惰な眠りの中に潜ろうとする。無意識にやわらかな体を抱き寄せると、汗のにじんだ眉間に皺が寄った。
「……んん」
小さな獣は目を覚ます。ほっそりとした指が、いやいやをするように俺のあごをかすめた。額に髭が触れて、痛かったのだろう。
「起きるか?」
かすれた声は雨音でほとんど聞こえない。花子は眩しそうに目をすがめる。すでに夕刻の部屋の中は照明もついておらず、眩しいわけもないだろうに。自分を拘束する腕に気がついたのか、状況確認をするようにわずかに首をもたげるが、一秒と経たないうちに再び腕の中へとうずもれてゆく。
「……なんでこんななってんの」
花子はまだ眠り足りないに違いない、もごもごと口の中だけで抗議めいた言葉を繰り返す。こんな、というのは、なんで自分が俺の腕の中で寝ていたのか、ということだろう。なんでそれを、俺だけのせいにしているのかは知らんが。
「お前が雷怖いつって来たんだろうが」
ベッドの上で本を読んでいたところにブランケットかぶって現れて、轟く雷鳴に耳をふさぎながらこの世の終わりみたいな顔をしていたのだ。放り出すのは良心が咎める気がしたのでやりたいようにさせてみれば、芋虫のように丸めた体を摺り寄せてくる。高い子供の体温というほどの歳でもないけれど、いつのまにか俺もその体温につられて眠り込んでしまったのだろう。
「……うそだあ」
しかし当の本人は覚えていないらしい。都合のいいやつめ。今度雷が鳴ってももう付き合ってやらねえぞ、と、言わぬうちに花子は顔を隠すようにベッドに突っ伏した。どうやら、ああは言っても実際は覚えてもいるし、照れてもいるらしい。寝ぼけ眼をこするように人のシャツに顔を摺り寄せ、安心したかのようにため息をついたかと思えば、
「……煙草くさい」
言うことはまったくかわいくない。いつもならば、だったら出て行けとつっぱねるところではあるのだが、今日はどうにもそんな気が起きない。昼寝の後のけだるさのせいだろう。開いたままの本に伸ばした手をひっこめて、もう一度この腕の中の温かさを抱きしめる。汗ばむ体にじわりとにじむ、少しだけ高い体温はこの上なく心地よかった。
夏のあなたは美しい。
空に積乱雲が立ち込めるころ、遠雷を恐れるあなたの背中が美しい。ごうごうと轟く雨を、雷を、遮ってくれとせがむあなたを守らなければならない。細い体を抱いたまま、時が止まってしまえと願うこのおこがましさこそが、あの夕立の残すもの。
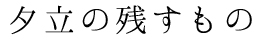
パオフゥ|ペルソナ2罰
