波の音にまぎれて届いた声に耳を疑った。こいつは何を言っているのか、と、思わず山田の顔をにらんでしまう。べたついた潮風が頬を撫でると、今日一日で日焼けした皮膚がうずくようだった。
「なにもそんなに怖い顔しなくてもいいじゃん……」
「どこが怖いと言うんだ」
ええ、怖いよぉ。と、不本意そうに文句を垂れる間も、山田と俺は歩みを止めなかった。真夏の街は夜になっても昼間の暑さが去らず、蓄熱したコンクリートは靴底を物ともせずに人を焼くようだ。遊んでいた仲間たちと別れてはや一時間、海沿いの道をぐだぐだとしゃべりながら歩く人間は俺たちの他にはいない。
「いいか、俺はお前を家まで送って行く。というか、現在送っている最中だ」
「うん。知ってるよ?」
「そして、お前を無事に家まで送り届けた後、俺は自分の家に帰る」
「それはダメ。南条君、一人は危ないから送って行ってあげるよ」
今に始まったことでもないが、山田の屁理屈はわがままと紙一重だと思う。わかっていて言っているのだからなおタチが悪い。
「ほう? それで? お前はそのあと自分一人で自宅まで帰るのか?」
「ひどーい。うら若き乙女にそんなことさせるの?」
「それでは堂々巡りだろうが。おとなしく――」
見下ろした先のまるい目がじっと俺を見ていた。水面のように揺れているのは、何故だろう。黒目の中に街頭の光が小さく映り込んで、思わずつないだままの彼女の手のひらを、ぎゅうと握りしめてしまった。山田はそれを、握り返す。握り返すのと同時に、口を開いた。
「ねえ南条君、みなまで言わせないでほしいなあ」
みな、とはなんだ。口に出せない疑問が腹の中で跳ねる。
続きの言葉を確認したくて、山田の唇が動くのを待っていた。やわらかいに違いないそれは、かすかに小さく震えている。いつもよりも顔が近い気がするのは、きっと今日の彼女が踵の高い靴を履いていたからだ。文字通り背伸びしているような、華奢な銀色の靴を履いているせいだ。
「あのね……圭くん、って、呼んでもいいかなあ」
「――は? なにを突然……」
「それでね、あとはね? わたしのことも、名前で呼んでほしい……。いつまでも山田山田って、他人行儀で嫌なんだもん。あとね? あと、ね……やっぱり、もっと一緒にいたい。帰りたくないの」
山田の指先に力が籠められる。握られているのは手のひらなのに、心臓をわしづかみにされたような気分だった。その熱さが……嫌ではない。嫌ではないが、どことなく恐ろしいような、罪の意識にさいなまれるような気がした。
波の音が遠くから寄せている。
「困ってる?」
「……少しな」
再び、引きずるような足音が響き始める。涼を運ぶ海風が頬をなでていった。
「そっかぁ……」
山田は少し悲しそうに笑った。俺は彼女のこんな顔が、ときどきたまらなく好きだと思う。ひまわりのように笑っている、いつも皆に向ける笑顔のほうがずっといい顔をしているのに、自分でもどうかしていると思う。
「――困っているが、嫌だというわけじゃないぞ」
もしも彼女の笑顔が曇っているのを晴らすのが、自分にしかできないことだから……などと考えているから、ならば、俺という人間は中々大層な趣味をしているのだろう。
「ほら、帰るぞ……花子」
はっと顔を上げた彼女から、思わず目を逸らしてしまった。
別に名前を呼んだのは、罪滅ぼしのためなんかじゃない。とは言うものの、たかだか名前を呼ばれたくらいで顔つきを明るくする花子も相当に単純な人間ではないだろうか。しかしまあ、あまり人のことは言えない。先ほど「圭くん」と呼ばれて、俺もそれなりに――正直に言うとかなり、嬉しかったのだから。
波がまた寄せる。今年は、海水浴をするには少し遅かった。来年はもっと早い時期に来よう。できることなら何度も来よう。来年は二人っきりでも、いいかもしれないな。
「何をへらへらしているんだ」
「だって嬉しいもん。えへー! じゃ、朝まで何しようか?」
「おい、そこは譲らんぞ。俺は帰る」
「ええっ!? やだっ、帰るならわたしついていくからね!」
「振り回すな! ええい、絶対に帰るからな!」
深夜にぎゃあぎゃあとわめいても、もう誰も咎めない。海岸沿いの道は人影もなく、頭上の三日月だけが静かに見下ろしていた。つないだままの腕を振り回して、じゃれあうように夏を泳ぐ俺たちを。
夏のあなたは美しい。
夜深はすべてが闇にあり、手探りすれども何ものにも触れ得ない。ただただ熱いと感じるものは、掴んだその手の生命ばかり。さらば、火球の昼よ、さらば、篠突く雨よ。熱帯夜を泳ぐあなたは、星の海を渡るだろう。去りゆく夏を追いかけるように、再び到来する季節へと手を伸ばしながら。
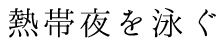
南条 圭|女神異聞録 ペルソナ
