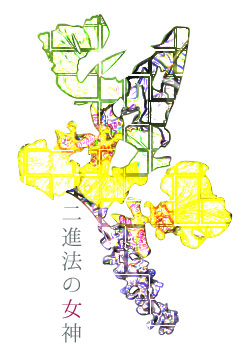ことの発端は、旋風寺家住み込みの執事である青木さんが腰を痛めたことだった。
「申し訳ありません舞人様……いやはや私も寄る年波には敵いませんなぁ」
詳しいことは本人しか知らないのだろうけど、何でも落としたものを拾おうと腰をかがめた拍子にぎっくり、いってしまったらしい。それが年のせいなのかどうなのか、それも僕にはわからない。
「いいんだよ、青木さん。青木さんだって僕に負けず劣らず働いているんだから、臨時の休暇と思ってゆっくりしてよ」
「舞人様……なんというお心遣いを……」
「やだなぁ、そんな言い方されたら照れるよ」
邸の中の青木さんの部屋は、さっぱりとしていた。余計なものはないし、調度品もシンプルなものでまとめられている。
窓辺に配されたベッドの中で、青木さんは僕に恐縮しきりの様子だった。家族同然に思っているんだから、そんなに気を遣わなくてもいいのに、と、僕は少しだけくすぐったくなる。
どうかゆっくりして欲しいと再度念押ししてから部屋を出ると、お見舞いに来ていた浜田君が心配そうに口を開いた。
「だけど舞人、青木さんがこうなっちゃあ食事なんかはどうするんだい?まさか、いずみさん……?」
「さすがに、いずみさんにそこまでお願いするのは申し訳ないよ」
「そうは言うけど舞人、料理なんてできるの?」
自慢じゃないが僕は料理の腕にだって自信はある。それは浜田君だって知っているはずだ。
じゃあなんでそんなことを聞くのかというのはつまり、僕にはそんなことをしている暇っていうものがないのだ。
「うーん……誰かにお願いしたいところだけど、よさそうな人っていうのは中々……」
「青木さんみたいに気のつく人って、本当に中々いないだろうからねぇ」
揃って、ため息がこぼれる。浜田君の場合は青木さんの料理がしばらく食べられないことが原因だろうけど。
けれど、本当にどうにかしなきゃいけない。いずみさんにお願いしても僕がやっても、通常業務に支障が出るに違いない。かといって、臨時で誰かを雇うにしても心当たりなんて皆無に等しい。
庭師から清掃員まで、邸の人事権は青木さんが握っているに等しいし、特別に誰かが必要なときはいつも青木さんにお願いしているからなぁ。僕は思わず天井を見上げた。別に、そこから誰かが降ってくるってわけでもないけど。
「こうなったら申し訳ないけれど、病身の青木さんに、“誰かいい人知りませんか?”って、聞くしかないのかなぁ……」
それがいいかもね、と、浜田君も頷く。
色々と問題は頭の中をよぎるけど、それだけ普段青木さんに頼りっきりだったことを痛感して、僕は反省していた。もっとしっかりしないと。
「あら、舞人さん。こちらにいらしたんですか」
「? なんだ、いずみさんか」
引き返して歩き出した僕らに後方から呼びかけたのは、秘書のいずみさんだった。華やかな顔立ちや服装からは到底想像もつかないほど――というと叱られそうだけど、とにかく彼女も気配りに満ちた優秀な秘書だ。年上の女性に対してそういう偉そうな評価をするのも、いわば総裁の“義務”だと大目に見て欲しい。
そのいずみさんは、僕の言葉を聞くとちょっとふくれて、
「なんだ、って、そんな言い草はひどいんじゃありません?」
「ごめんごめん!そんなつもりで言ったんじゃないよ。どうしたんです?」
こういうところはまだ少女っぽいというか、かわいい人だと思う。とは言っても僕にとっては姉のような人で、気の置けない存在だ。
「どうしたもこうしたも、青木さんがいつの間にか舞人さん専属のメイドさんを手配してたんです。それをお伝えしようと思って」
「専属メイド!?」
「それって、青木さんが休んでる間に舞人の世話をしてくれるっていうこと!?」
「はい、専属ですから」
青木さんの手際のよさに感心しつつ、メイドという言葉のインパクトに驚きを隠せなかった。
僕が何を考えているかはともかく、浜田君ときたら、
「いいなぁ〜舞人、専属のメイドさんに身の回りのお世話、だって!」
ぐりぐりとわき腹を肘で突いてくるもんだから、僕は当然反対側に身を捩じらせる。
「な、よ、よしてくれよ浜田君!」
「あれ?舞人ってば何考えてたの?」
「いや、そういうことじゃ……」
「やらしー! ね、いずみさん。そのメイドさん見た?かわいい?」
「え? はぁ……まだ見てませんし、かわいいかどうかも知りません!」
いずみさんはきっと、呆れているんだろう。そりゃ確かにメイドとしての仕事ぶりに容姿なんて関係ないけど……まぁでも、一般論としてかわいい子のほうがいいに決まってる。仮にいずみさんに執事がつくとしても、その彼がかっこいい男性であるほうが、いずみさんだって喜ぶに違いない。
浜田君はいずみさんの言葉もなんのその、未だ見ぬメイドに想いを馳せているらしい。
「なーんだ。でも、いつ来るんです?」
「ええと、青木さんが言うには……あら、今日からだそうです」
いずみさんは、手元のクリップボードをペンのお尻で辿りながら微笑んだ。彼女としても、早く来て貰ったほうが助かるんだろう。
「今日?そりゃまた早いね」
「ええ。……えっ!?」
「どうしたの、いずみさん……?」
顔をこわばらせていたいずみさんがゆっくりとこちらを向いた。クリップボードのメモをこちらへ見せるから何事かと覗き込むと、そこにはありえない数字があった。
「職歴……七十年……?」