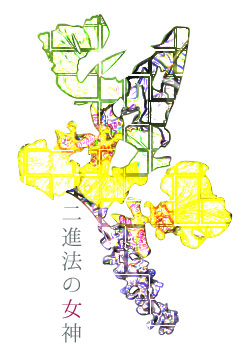「少なくとも八十代後半だよなぁ……」
「うん……じいちゃんより長生きだ」
まもなく到着するという彼女、名前はジェーンさん、というらしい。とにかくその彼女が来るのを応接室で待っている僕らの気分は、ほとんど灰色に近かった。ちなみに浜田君は興味本位でここにいるだけだ。
いや、いや、別に、おばあちゃんがイヤだってことじゃない。心配しているだけだ。
だって、もしかしたら九十歳を軽くオーバーしているかもしれないご婦人に、一体誰が身の回りのお世話なんて頼めるだろうか。どっちかって言うと、僕らのほうがお世話しなきゃいけないんじゃないか。
青木さんのメモには『信用できる人物です』と書かれていたけれど、今回ばかりは青木さんにも手違いがあったんじゃないだろうかと、疑わざるを得ない。
なんだか頭痛すら感じながらソファーにのけぞっていると、応接室の厚い扉がノックされた。
「はい?」
「舞人さん、ジェーンさんをお連れしました」
顔を覗かせたのは、いずみさんだった。どういうわけか、彼女は僕らと違って気が重いとは感じていないらしい。それが証拠に、ずいぶん楽しそうな表情が張り付いていた。
「ああ、どうぞ」
「えっ!?ちょっと待ってよ舞人、僕まだ心の準備が――」
当事者でもないのにどういうわけか焦っている浜田君は放っておいて、僕は重い扉がゆっくり開くのを見守っていた。
ああきっと、しわくちゃの顔、下がった目じり、真っ白な頭髪、曲がった腰。これらが現れるものだと思っていたのに――
「失礼します、ジェーンでございます」
耳に届いたのは張りのある軽やかな声。正直僕は、目の前で起こっていることを信じられなかった。
つやつやの頬、ぱっちりした大きな目、お下げに結われた薄桃色の髪、作り物のようにすらりと伸びた四肢。身に着けているのはひざ上丈の紺のワンピースと、細かいレースで縁取りされた白いエプロン。絵に描いたようなメイドさんだ。
「青木さんのご紹介で参りました。しばしの間ではございますが、お世話になります」
これがジェーンさん? メイドとしての職歴七十年の大ベテランである、ジェーンさん?
どう見たって、いずみさんと同じくらい、つまり、二十代にしか見えない。ふわふわと微笑んでいる表情は、一般的な二十代の女性よりもっと若い、というか、幼いと言ってもいい。
僕は助けを求めるように、浜田君を振り返る。期待はしていなかったけど、やっぱり彼も唖然として硬直していた。
「……」
「……」
沈黙が部屋を支配する。
「あの、」
それを破ったのは、ジェーンさんだった。
「あのう……どちら様が、舞人様でいらっしゃいます?」
呆然と口を開けることしかできていなかった僕らは、困ったように眉を下げる彼女に笑われてしまった。
「ああ、ええと!彼です!こっちが舞人!」
浜田君が慌てたように僕を指差す。その顔がなんとなく赤い気がするけど……まぁ確かに、かわいい女の子――いや、女の人、なのかな――を見ればそうなるのもわからないでもない。正体は、不明だけど。
いやしかし! 人を見た目でどうだのこうだの言うべきではない。彼女がジェーンさんであることは間違いないようだし、青木さんが手配してくれたのなら問題もないんだ。総帥の心得、ひとつ、無闇に人を疑うことなかれ。だ。
「ええと、ジェーンさん。こちらこそ、しばらくの間よろしくお願いします」
「はい、よしなに。それから私のことはジェーンとお呼びくださいませ」
「僕は誰でも“さん”付けしてるから、僕に合わせてくれると嬉しいな。ところでこっちは浜田君。僕の親友だ」
「かしこまりました。浜田様、でいらっしゃいますね。よろしくお願いいたします」
「ははははい!よよよろしく!」
「緊張しすぎだぞ、浜田君!」
「うるさいよ舞人!だってこんな……その、なんというか、若々しい人だって思ってなくて、びっくりしてるんだよ」
……うん。どう考えたっておかしい。
彼女はどこからどう見ても八十代には見えない。いいや見た目とかそういう問題じゃない。彼女が老女であるはずがない。どれだけ年嵩に見積もってみても、二十代後半が関の山ってとこだろう。まさか青木さんが『七年』と『七十年』を間違えたのかと思ったけど、祖父の代から旋風寺家に勤めている青木さんが、たかだか七年の勤続をもってベテランなんて言うはずがない。
ここは本人が目の前にいるのだ。推測ばかりせずに聞いてみたほうがいいだろう。
「僕も驚いてるよ。ジェーンさんは、失礼だけどおいくつなんです?」
かわいらしい桃色のお下げを揺らしながら、彼女はにっこり微笑んだ。
「はい。製造されて今年で七十年でございます」