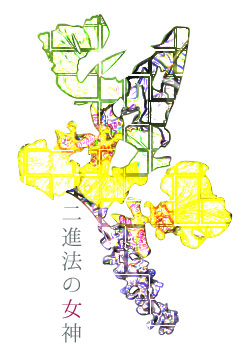まるで世界の終わりのような夕陽だった。
どこもかしこも赤く染める太陽を背後に、直角に曲がった煙突の影が十字架を作っている。
『あの人を殺さないでください』
ジェーンさんは祈るように、僕に懇願した。もしも彼女が涙を流すことができる存在だったなら、両頬を伝う雫を僕は目の当たりにしたことだろう。
その光景を思い出しながら、僕は目の前十字架を見上げる彼を、見ていた。彼は何を思い、ここに立っているのだろうか。僕にはわからない。それは人間と人造人間の差異ではなく、100年の間生きている彼と、16年間しか生きていない僕の差異なのだろう。
右腕を負傷した彼は、回路に何らかの不具合が発生したのだろうか、立ち去ろうともしなかった。
「ユリウス」
呼びかけると、彼の目に驚きの色が浮かんだ。
「君は……あのときの」
あのとき、というのはきっと、車で事故を起こしそうになった日のことだろう。今気づいたかのような口ぶりから察するに、彼は巨大ロボットで街を破壊した連中の、単なる協力者として利用されたに過ぎないらしい。
「そうか……君がマイトガインのパイロット……」
ユリウスはかすかに、口元に自嘲の笑みを浮かべた。
「……暗殺に失敗したのは、初めてだ」
その言葉がどこか嬉しそうなのは、後から思い返せば、不完全であることが人間らしさであるという証だと、彼が思っていたからかもしれない。人を殺すことだけを目的として作られた彼が、ようやくその存在目的を覆したのだ。
「ユリウス、あなたは――」
僕は何を問えばいいのかわからなかった。どうしてこんなことに手を貸したのか、これからどうするつもりなのか、思い浮かぶことはあるけれど、何一つとして言葉にならない。とても軽々しく何かを尋ねる気にはなれなかった。
彼は、僕の言葉を待たずに語り始める。乾いた声色はどこまでも、孤独以外の何かを感じさせない。
「ああ、俺は人造人間だ。暗殺専用マシーンとして重い十字架を背負って、長い間生きてきた」
ユリウスの頬が夕陽を浴びて、橙色に染まっていた。口の動きも言葉の発音も人と変わらない。そして、人殺しのために作られたという己の境遇に対して、「重い十字架」 と自ら断罪している。それは人間とどう違うのだろうか。
「いつか、人間と同じになれる日を夢見て。今日まで」
僕に背を向けて十字架を仰ぐ彼は、これまでも己の罪を悔やんできたのだろうか。
誰にも理解されることのない百年の孤独、許す者のいない贖罪。僕には想像もつかない。
「そして、今なら――人間になれる」
違う、あなたはもう人間だ。
僕はそう言いたかった。
もう十字架を背負うことはない。もう人を殺さなくていい。あなたのことを許す存在はすぐそこにあるのだ。
なぜならば――
「――ユリウス!」
彼女は走る。息切れも知らない体、彼と同じ作られた運命を背負った彼女が駆けてくる。
「ジェーン……」
まるで体当たりでもするかのような勢いで、ジェーンさんはユリウスの胸に飛び込んだ。数十年分の想いを、ユリウスはそのまま微動だにもせずに受け入れているように見える。その表情は驚きから、やがて穏やかでやわらかいそれに変わっていった。
「ずっと、ずっと探してた……よかった、あなたが無事で」
「ジェーン、」
「よかった……会えて、よかった」
「そうか……」
変わらぬ姿を目の当たりにして、彼は何を感じたのか。瞳の中からは何も窺えない。まだ未熟な僕には、二人の間の感情がどういうものなのか判断できなかった。
それは男女としての恋愛感情なのかもしれないし、まるで女神のような慈愛に満ちたジェーンさんの、家族愛や母性愛に似た愛情なのかもしれない。そのどちらにせよ、きっと彼女の愛はユリウスを救うのだろうと、僕にはそう信じられた。
夕陽と十字架を背景にした二人は、まるで絵画のように美しかった。時がとまったかのような光景に、僕は思わず息を呑む。ユリウスはまだ動く左手で、そっとジェーンさんの背中に触れた。抱き寄せるでもなく、ただ触れるだけ。ためらうような仕草は、きっと人造人間にはできない動きだ。
「お前はなんで、ここにいるんだ?」
ユリウスはようやく思い当たったかのような口ぶりでジェーンさんに尋ねる。彼女は顔を上げ、
「これまでと同じように、今は旋風寺様のお邸で働いているんです……それで、あなたの写真を見て、あなたに会えると思って」
「そうだったのか……」
僕はそろそろこの場から退散したほうがいいのだろうと思って踵を返したが、ジェーンさんに呼び止められてしまう。
「舞人様!」
振り返ると、今にも泣き出しそうな顔のジェーンさんがそこにいた。
「あの、彼は、ユリウスは……」
どうなるのか、と聞きたいんだろうと思った。
処分されるのか。それとも人間と同じように法律で罰せられるのか。
ジェーンさんはユリウスの服を、しがみつくように握ったままだった。それは僕が見た中で、最も頼りない彼女の姿だった。とても放ってはおけないような姿に、思わず僕は手を差し伸べたくなる。けれど、そんなことをする必要などなかった。
彼女には彼がいる。そして、彼には彼女がいる。
「僕は――いや、僕がどうこうする問題じゃないと思うな」
きっとユリウスはもう、暗殺などしない。きっと二人は共に生きていくのだろうということが、僕にはわかる。
「人は変わることができるのだから。生きている限り、変わることができるのだから。新しい生き方を見つけるのもいいんじゃないかな。二人ならきっとできる。僕はそう信じていますよ」
僕がそう伝えると、ジェーンさんは何度も何度も頭を下げていた。ユリウスもまた、僕に心からの感謝の言葉を述べてくれる。僕は何もしていないのに。そう苦笑して、僕はその場を立ち去った。去り際に聞こえた会話の一部が、今でも耳に残っている。
「――美術館で、」
「え?」
「美術館で、絵を見ていた。聖母子像の絵だ」
「そう……そうなの……」
「女神の顔が、お前そっくりだった」
「ユリウス……」
僕は時々こんな夢を見る。遠い未来のどこかの世界、二人は手を取り合って砂漠を渡る。荒れ果てた地上に、彼らのほかに人影はない。
その世界で二人は、最初で最後の機械仕掛けの恋人になる。
そんな夢を、見ていた。