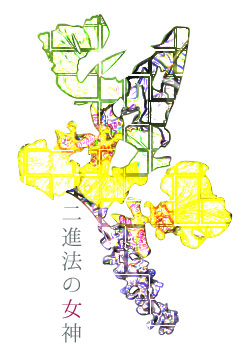ようやく上半身だけ起き上がることができるようになった青木さんの部屋を訪ねた僕は、聞きたかったことをぶつけてみた。ここ数日忙しくて、顔を合わせるのも久しぶりだ。
「青木さんも人が悪いよ。どうせきっと、僕らの反応を楽しみにしてたんでしょ?」
「はっはっは、いやいや、そんなことはございませんよ」
「どうかな?だったらどうして、いずみさんにも直前まで彼女が人造人間だってことを言わなかったんだい?」
そう、彼女は人造人間だったのだ。
詳しいことは僕も知らないけれど、人造人間の製造は現在では禁止されている。それこそ彼女が作られた付近の数十年には研究が繰り返されていたらしいけれど、何でも生命倫理がどうとかいう団体と、人造人間を悪用する連中の台頭で、あっという間に廃れてしまったらしい。
そうは言っても超AIを組み込まれて感情すら持ってしまった人造人間を“処分”することなど許されることじゃなく、今でもほんのわずかな数の人造人間が“活動”しているらしい。
ジェーンさんは、人造人間研究が進み、人の生活に役立つ各種の機能に特化した存在を作ろうとしていた頃の、メイドやシッターとしての特性を強化されたプロトタイプだそうだ。
作り物のように整った体は、何を隠そう本当に作り物だったなんて皮肉にもほどがある。
「おや、申しませんでしたかな」
「はぁ……まぁ、いいよ。でもよく人造人間の知り合いなんていたもんだ」
「ええ。彼女とはいつでしたか、そうそう、彼女が当時の首相のお邸に勤めていた頃に、パーティーか何かで知り合った縁ですよ」
「へぇ……ナンパでもしたのかい?」
「とんでもない。その仕事ぶりに驚きましてね。まだお若いのにと話しかけたのがきっかけでした。……その首相は汚職で地位を追われ、彼女が路頭に迷ったときに、私が次の仕事を紹介したのです」
「なるほど。じゃあ今回のは、青木さんへの恩返しってことなのかな」
「そうかもしれませんなぁ」
思い出を語る青木さんの目はとても優しかった。それと同じくらい、ジェーンさんの目も優しいと思う。
長く生きてきた彼らには、十六歳の僕なんかには想像もつかないように、世界が見えているんだろうか。
僕には想像もつかないけれど、こんな優しい目をした人ばかりになれば、きっと世界はもっと早く、平和になるに違いないと思った。
「失礼します。お茶が入りました」
噂のジェーンさんが、ティーセットを載せて部屋に入ってくると、ふわりとラベンダーの香りが漂う。とっぷりと暮れた夜更けに、甘い緞帳が垂らされたようにも思えた。
「いい香りだね。お茶に何か入っているのかな?」
「はい。ラベンダーのハーブティーでございます。ラベンダーは神経痛によいので、是非青木さんにと思いまして」
「これはこれは……では、いただきましょうか」
「なんだ、僕じゃなくて青木さんがメイン?」
「もちろん、舞人様にもぴったりですよ。ラベンダーには人の気持ちをリラックスさせる効能もございます。しっかり休養なさるのも、上に立つ方の責務でございますよ」
「……ジェーンさんには敵わないなぁ」
「ほっほ、私の目に狂いはなかったようですな」
「恐れ入ります」
二人分のお茶を仕度して、ジェーンさんはそこに立って控えている。
口に含んだ紅茶はほのかに甘く、なるほど確かにこれなら心地いい眠りに誘ってくれそうだった。
彼女は食事を摂らない。家事全般をまかなえるように、調理時の味見のための味覚センサーが搭載され、多少の食物を摂取はできるけれど、基本的に内臓に相当するものはない。人造人間だから、それはしょうがないのかもしれないけれど、誰よりも働いてくれるジェーンさんにこそ、このお茶を味わって欲しい――たまにはゆっくり休んでほしいとも思う。
睡眠すら必要ない彼女は、僕だけでなくいずみさんの補佐も少しだけれどやっているみたいだ。不謹慎にもほどがあるけど、いずみさんがぼやいた「青木さん、もう少しだけ寝込んでてくれないかしら……」 というのにもほんの少しだけ、同感だった。青木さんが回復すれば、彼女はここを去るだろう。彼女さえよければ、ずっとここで働いてほしいというのがいずみさんの、そして、僕の気持ちだった。