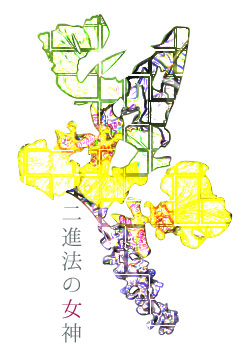という話を浜田くんにすると、彼の興味を引いたのは僕とは違う部分だった。
「ブラックガインのときもそうだったなぁ」
懐かしい名前が出てきて一瞬、喉の奥が熱くなる。
応接室のソファーに腰を下ろしたまま、僕は少し前のことを思い出そうとして、やめた。向かい合って座る浜田君は、僕の様子に気づいていないようだった。
「難しいんだよ、やっぱり。対人間用に作られた人造人間は、コミュニケーションの手段が会話くらいしかないからね。見たことはないけど、多分かなり高度なプログラムがされてる」
それはそうだろう。例えば一般にも普及しているコンピューター端末は、正確にコードを組んでやればこちらの意図したとおりに動いてくれる。だけど超AI搭載のロボットや、簡易版のAIを積んだ量産型のロボットは意思の疎通とも呼べる機能を搭載している。それは人の発する言葉の単純な意味だけでなく、表情や言葉の調子からそれ以上の意味を推察するらしい。そういう分野に飛びぬけて詳しいわけでもない僕でも、それがとてつもなく膨大な情報を抱えたAIだということは理解できた。
「下手にいじれば、」
「おじゃん、だろうね」
人の役に立つのが、自分が存在する意義なのだと語っていた彼女を思い出した。
彼女にとって、自分の思考を伝える言葉というものは大切なものに違いない。そしてそれは、僕ら人間となんら変わるところがないのだ。
「でもいいじゃないか、いじらなくてもさ。ジェーンさんは、そういうところも含めてすごく魅力的だし」
「ふぅん?」
別に僕はいじるとも言っていないのに。そう言いだした浜田君は、少し焦っているように思えた。
「な、なんだよ舞人」
「別に?」
僕の親友は惚れっぽいところがある。大方今回もまたそうなんじゃないかと思って、僕はちょっとしたカマをかけてみることにした。
「人造人間も恋をするのかな」
すると浜田君は紅茶の入ったカップを落としてしまう。絨毯が敷いてあったからカップは無事だけれど、絨毯には琥珀色のシミが広がった。
「あーあ、何やってるんだい」
「舞人がおかしなこと言うからだろう!」
「おかしなって?」
「そりゃ、……もういいよ……」
脱力した様子にぶっと噴出すと今度こそ浜田君ににらまれてしまった。この場合、絨毯を汚された家主の僕が怒って然るべきじゃないだろうか。
まあ、いいか。
「ジェーンさーん」
僕が一声かけると彼女はすぐにやってくる。
「はい、こちらに」
「紅茶をこぼしてしまってね、すまないけれど……」
「あらまあ。かしこまりました。ちょっと足元、失礼いたします」
ジェーンさんはエプロンのポケットから雑巾だとか、溶剤の入った容器だとかを手際よく取り出す。いつも思うけれど、あれは本当にポケットなんだろうか。ポケットでなければなんなのか、なんてことは、あまり考えたくもないけど。
「ごめんなさい、僕がこぼしてしまって」
「いいえ、お気になさらないでください。早いうちでしたら紅茶のシミはよく落ちますの」
浜田君はこの出来事すらチャンスとでも言いたいのだろうか、ジェーンさんと見詰め合って談笑を始めた。どうして落としたのか、とか、もしかして紅茶が熱すぎたのなら申し訳ない、とか、ジェーンさんが気を回しているのを見ているとどうにもいたたまれない。
「僕がおかしなことを言ったせいさ。ごめん、ジェーンさん」
「あらあら、舞人様まで。ようございますよ、わたくしの仕事ですから」
手際よく絨毯のシミを叩いて落としながら、彼女は笑う。黙り込んでしまった僕らのぎこちない空気をほぐすように冷やかした。
「舞人様、一体なんておっしゃったんです?」
「え?――ああ、それは……」
どうしよう。
そのまま「人造人間は恋をするのか話していたんです」 なんてのはなんだか失礼な気がするし。
僕らが口ごもっているのを見てジェーンさんはどう納得したのか、したり顔で何度か頷くと、
「舞人様も浜田様もお年頃ですものね」
「え、」
「ちょっと待って」
「ご、誤解です!」
「あら、別におかしなことじゃございませんよ」
参った。このときばかりはジェーンさんがなつっこいおばあちゃんのように見えた。
わかってますからと言わんばかりの顔をされると言葉に詰まるが、覚えのないことでこんな扱いをされるのは僕も浜田君も望んじゃいない。
「違うんだよ、ジェーンさんは好きな人とかいないのかなって」
当たらずとも遠からぬことを言うと、ジェーンさんは少し、戸惑ったような顔をした。これは、もしかして――
僕らは思わず身を乗り出してしまったけれど、
「……いいえ」
ジェーンさんは小さくかぶりを振るだけだった。さびしげに微笑む彼女のこれまでに、一体何があったのか。僕らには想像もつかないし、誰も知らないのだろう。ただ、彼女の中に流れている時間は人間と同じであり、感情を持った彼女にも、人間と同じく悲しいことも嬉しいこともあったに違いないと、それだけは僕にも容易に推測できた。
いずみさんがなんとも言えない顔で言っていたけれど、ジェーンさんは“皺”がうらやましいらしい。
『ひとつずつ歳を重ねていくこと、知らないことが減っていくこと、少しずつ最期に近づいていくこと、経験を積んで美しくなった人のお顔は、とてもすばらしいものです』
いずみさんは自分の目元がどうこう口元がどうこう言っていたからどういう状況だったのかわからないでもない。
けれどないものねだり、そう言ってしまうのはあまりにも軽々しくて、僕は彼女の存在自体について考えることが多くなった。
人間である僕は、いつか死んでしまう。もちろん人造人間の彼女も、致命的なダメージを受けたり、物理的な身体がなくなってしまえば、それは死と言っていいのかもしれない。ガインたちも同じだ。
けれど彼らはその記憶とよべるものを、いくらでもバックアップできる。人間である僕と違って。
死ぬということの意味が希薄になるほどに、生の意味も薄まってゆくのだろうか。
メメント・モリ、死を想え、という言葉がある。生の実感は死を意識すること――なんだか難しいけれど、今ようやく少し、わかった気がする。
きっと彼女は僕らの、限りのある時間がうらやましいのかもしれない。
彼女は今までに恋をしたのだろうか。もしもそれが人間相手のものであったら、彼女の苦悩はどれほどのものだったろう。想像してみたところで答えなんか出ない。何故なら僕と彼女とは全く別の種類の存在だからだ。
そしてその差異は、気にしないと思えば思うほどに、埋まらない溝として彼女を苛むのだろう。