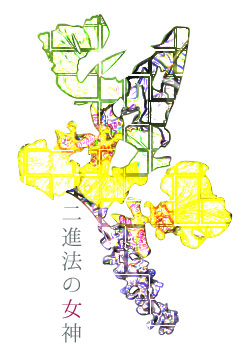僕は今、ヌーベルトキオの街中をスケボーに乗って駆け巡っている。
「みなさーん! 回々軒のバカうま屋台ラーメンをよろしく!」
片手には出前箱(もちろん空)、もう片手に携えたビラを、これでもかというくらいに派手にばら撒く。
悪漢に襲われ、一度手にした評判を失ってしまった店に、もう一度注目してもらうにはこれくらいやらないとだめだ。
「出前も超特急にて承っておりまーす! よろしくー!」
その結果は上々で、道行く人たちもビラに興味を持ってくれたみたいだった。
「ん? 回々軒のバカうまラーメンかあ……」
「出前もやってるんだ」
「ちょっと頼んでみる?」
そんな会話を背中に聞きつつ、さらに先のエリアに進もうとしたところ、僕は見知った顔を見つけた。というより、これだけ派手なパフォーマンスをしていたのだから彼女のほうが先に気がついていたに違いない。
「舞人様、」
「ジェーンさん」
ポシェットのようなものを提げた彼女のほうへ向かい、スケボーを止める。
「何なさってるんですか?」
その声音には咎めるような響きはなく、むしろ単純な好奇心のようだった。
「ああこれ、実はね……」
評判のラーメン屋に行こうとしたら、当のラーメン屋が暴漢に襲われていたこと。そのラーメン屋で吉永サリーちゃんが働いていたこと。話を聞く限りじゃ店の側に非はなさそうだし、自分としても再建に協力したいと思っていること。かいつまんだ事情を話すと、ジェーンさんは晴れ晴れとした顔つきになる。
「さすが舞人様です。助けを求める方に躊躇なく手を差し伸べるのがまごうことなき真の正義です!」
「え? そうかい? い、いやぁ……そこまで褒められると……」
嬉しい。嬉しいには嬉しいけど、彼女の顔がどうにも、「孫を褒めるおばあちゃん」 みたいだということには気がつかないフリをしていよう。
「わたくしもお手伝いに行ってよろしゅうございますか?」
「大歓迎だよ! 人手は多いに越したことはないから――でも、仕事中なんじゃないの?」
「いえ、今日から青木さんがお仕事をなさるので、わたくし今日一日はお暇をいただいております」
「ああ、そうだったんだね」
ようやく復帰できた青木さんだけど、まだしばらくはジェーンさんにもいてもらおう。というのが、主にいずみさんと、それからなぜか浜田君の強い希望だった。青木さんがなんとも言えない微妙な顔をしていたのは少し同情するけれど、この際二人ともに働いてもらってもいいかなと、僕は思っている。
「お休みなのに働かせるのは気が咎めるけれど、よかったら手伝ってほしいな。場所は……」
僕は回々軒の場所を軽く説明し、彼女と別れてビラ配りを再開した。ほどなくしていずみさんたちから出前の依頼が入り、直後に謎のロボットが襲いかかってくるのだけど――
そのときジェーンさんたちも、危機的な状況に陥っていたことを知ったのは、後になってからのことだった。
「工場長……」
「幸いにして、損傷は軽微です。破損したパーツの替えもありますし、外装を整えてあげれば元通りですよ」
僕らの目の前には、うつぶせで横になっているジェーンさんがいる。作業台の上の彼女の顔だけが横を向いていて、目も口も中途半端に開いたままでまったく動かない。こうしているとまるで人形だった。どこかのお店から運ばれた、よくできたマネキンにも見える。
「ごめん、舞人……僕が……」
浜田君は責任を感じているらしかった。
あの直後に回々軒を襲った暴漢は、店主のサカモトさんによって撃退された。ただし、サカモトさんの相棒のタナカさんは袋叩きにあって大怪我、浜田君も突き飛ばされたときに打撲、サリーちゃんと哲也君もそれぞれ擦り傷を負っていた。擦り傷程度で済んだのは、ジェーンさんが二人をかばって暴漢に殴られたからだ。そして、まだ目覚めない。
「気にしないでくれ。きっとジェーンさんもそう思ってるよ」
「うん……」
「打ち所が悪かっただけだよ。スキャンして確認したが、重要な機能には何の影響もない。ただ中枢回路と駆動系をつなぐコードが、ちょうど切れてしまっただけだ。大丈夫、すぐに直る」
工場長もまた、浜田君を励ますように朗らかな口調だった。
暴漢に殴られた箇所――ちょうどうなじのあたり――は、皮膚の代わりのラバーが断裂し、内部に張り巡らされた無数のコードが一部露出していた。
こうして見ると、確かに彼女は人間じゃない。それは明らかで、だけど、人間と同じくらいに痛々しい光景で、少しぞっとする。不気味の谷と言うのはこれのことだろうか、と考えて、どういうわけだか申し訳なく、そして自分を恥ずかしく思った。
そんなことを考えているのはどうやら僕だけらしい。工場長がスタッフに声をかけると、早速作業が開始される。まるで手術のようだけれど、使っている工具は人間に使用するものじゃない。
すごく、不思議な光景だった。僕は見ていられなくなってとっさに目をそらしてしまう。
「……でも、ジェーンさんらしいな。暴力的なことは嫌いそうだと思っていたけれど、やっぱりそうだったみたいだね」
僕はなんとなく、彼女は非好戦的だとは思っていたけれど、思いついたことを言ってみた。浜田君によると、ジェーンさんは戦うような素振りは一切見せず、徹頭徹尾サリーちゃんと哲也君を守ろうとしていたらしい。暴漢に殴られるときにも、一切の抵抗はしなかった。
「ロボット三原則、っていうのがあってさ」
浜田君は、修理中のジェーンさんを見つめていた。見つめながら、続けた。
「その中の一つで決まってるんだ。ロボットは、人間に対して手を挙げちゃいけないんだよ」
作業台の上では、小さなショート音が上がった。回路の接続に成功したんだろう。工場長たちの安堵の溜息が聞こえた。
「多分ジェーンさんはそれに従ったんだ。たとえ悪党が相手でも」
「……」
そうだろうか。
僕はその場にはいなかったけれど、想像するのは難しくない。
ロボット三原則、確か、人間に危害を加えないことでさらに人間に危険が迫ることが予想される場合には、その危険を排除するために抵抗してもよかった気がする。ジェーンさんは立ち向かう大義名分があったにも関わらず、そうしなかった。
その理由は多分――
「僕は、そうじゃないと思う」
「舞人……?」
「確かに浜田君の言うとおり、そういうルールがあるのかもしれない。でも僕は、彼女がそういう性格だからだと思う。ジェーンさんは戦いとか、そういうのを好む人じゃない。だから戦わなかったんだ」
浜田君は虚をつかれたような顔をしていた。僕の言っていることは単なる言葉遊びなんだろう。自分でもよくわかっている。だけど、僕自身がそう信じたかったんだ。
「ジェーンさんの手はね、暖かいんだよ」
僕は自分の手を、握り締めた後にもう一度開いた。
「もちろん体温なんかじゃない。かなり高性能の冷却装置を内蔵していても、わずかに蓄熱するらしいんだ。その温度は、三十六度四分。人間の体温だ」
はっと息を飲む浜田君の目は、心なしか輝いていた。
そう、僕らは信じたい。彼女が人でないながらも、人に限りなく近い愛すべき存在であるということを。
信じているのだ。