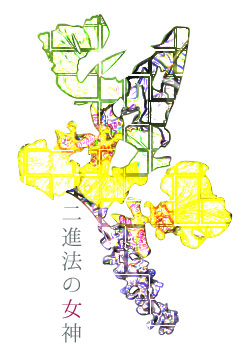「もしかしてあまりにも昔過ぎてもうお亡くなりに……」
それから数日後、僕と浜田君はあるものを挟んで応接室のソファに向き合って座っていた。
話題はそれとは全く関係なく、もっぱらジェーンさんのことだった。浜田君、もしかして本気で彼女のことを……と邪推の一つもしたくなる。それと同情も。何故ならジェーンさんにはどうやら、想い人がいるらしいから。浜田君だってそれを承知した物言いではあるけれど、中々厳しいのではないだろうか。いや、浜田君が魅力に欠けるというわけでなく、なんとなくジェーンさんは、とことん一途な印象があるからだ。仮に想い人がすでに故人であったとしても、彼への想いをいつまでも抱えているに違いないと僕は思う。
「いや、それなら彼女だってわかってるだろうさ。せいぜい二、三十年前のことじゃないのかな」
彼女の想い人がどういう人なのか、僕らは知らない。ジェーンさんに尋ねるのもなんとなく憚られる。こんなときいずみさんなら女同士、気兼ねなくたずねてくれそうなものなのに。
「どうなんだろうね……青木さんは知らないの? 古い付き合いなんですよね?」
「はぁ……いやさすがに、そういうことまでは存じませんなあ」
水を向けられた青木さんも、数日前に始めて聞いたこの話題はやはり予想外とでも言うべき反応だった。
「知ってる方が怖いよ」
「確かに」
「聞こえておりますぞ」
おっと、まだまだ我が家の執事は現役だったらしい。
肩をすくめる僕らを少しだけ笑って、青木さんは応接室から下がった。
「まぁとにかく……この線条痕なんだけど……」
そうだった。僕ら二人が向かい合っている理由は、机の上のライフル弾にある。
「一致する銃を調べたらとんでもないことがわかってね」
「とんでもない?」
この弾は今日、僕に向かって――正しくは、マイトウィングの左翼に向かって――放たれたものだ。弾が手元にある、ということはすなわち命中したということだ。僕個人を狙っていたのなら外れなのかもしれないけれど、飛行中のマイトウィングに当たればそれがどこでも大事故につながる可能性はある。
立場上命を狙われることも少なくはない。けれど、音速で飛ぶマイトウィングが対人用のライフルで狙撃されることなんて初めてだった。スナイパーはよほどの腕利きに違いない。
「それはとんでもない腕のスナイパーだった、っていうことかい?」
「そうじゃない……まぁ、確かに腕はとんでもないけど、存在自体がとんでもないんだよ」
「いやにもったいぶるなあ、どういう人物なんだい?」
浜田君が机の上に差し出したのは、一葉の写真だった。
鋭い視線、こけた頬。見覚えがあるのはどうしてだろう。考え込む僕の脳裏に、ある雨の日の光景が広がった。心臓に氷を押し付けられる、とでも言うような、ぎょっとする感覚が再び僕を襲う。
「この人――」
あのときの男性に違いない。
数日前の雨の日のことだった。帰宅途中だった僕の乗った車が、突然前に飛び出してきた男性を撥ねそうになった。写真の彼はあのときの男性に間違いない。
まさかあのときの恨みで僕を狙撃したんだろうか。考えられる動機なんてそれしかない。けれど、彼はあのとき恨みがましい視線の欠片すら、僕らには向けなかった。
それが、どういうことだろう。殺意にかわった悪意を向けられたことに対する恐怖が今更こみ上げてくる。
浜田君はそれを知る由もないので、淡々と写真の説明を続けるだけだった。
「名前はユリウス。ただの人間じゃない」
「どういう意味だい?」
「……舞人、この写真がいつのものかわかる?」
セピア色の写真は、どう考えても最近撮られたものとは思えない。こんな色合いの写真は、祖父のアルバムでも珍しいものだ。
「わざとこんな色にしてるわけじゃないんだろう?」
「もちろんさ。指名手配の犯人写真は、カラーのほうが情報を集めやすいに決まってる」
「ということは、こんな色の写真しか“手に入らなかった”わけか……」
つまり、この程度の技術しかなかったころの写真か、原版あるいは元データの劣化のせいでこうなったということだ。いずれにせよ、相当昔の写真ということになる。それはすなわち、彼もまた過去の人間である可能性が高いということだ。
「じゃあ、今回の犯人は彼の銃を手に入れて、それで僕を狙ったっていうのかい?」
「それも考えられないこともないけれど……やっぱり音速で飛行するマイトウィングを狙撃するなんて人間のできることだとは思えないんだよ」
浜田君は一呼吸置く。
「実は、彼は人造人間だっていう噂なんだ」
一瞬、呆気にとられてしまった。確かに、確かにそれは辻褄が合う。けれどにわかに信じられるものじゃない。
が、
「……けれどジェーンさんだって人造人間なんだ。可能性はある」
そういうと、浜田君も同感といわんばかりに頷いた。
「彼は百年前に作られたらしい。ジェーンさんよりもずっと、旧式のボディのはずだ。それでも狙撃の演算能力なんかは今のガインたちに匹敵すると思って間違いないね」
「百年前の人造人間か……」
「けど、どうして舞人を狙うんだろう?」
それは僕だって聞きたい。先日の恨みなのかもしれない。
「けど、殺し屋ってことは誰かに雇われてる可能性もあるよな……」
誰かの差し金かもしれない。そちらであれば心当たりはたくさんあるけれど。嘆かわしいことに。
二人してうんうん唸っている応接間に、控えめなノックの音が響いた。
「失礼します、お茶をお持ちしました」
ジェーンさんだった。穏やかな笑みを浮かべつつ、いい香りの紅茶を配膳してくれる。
「もう遅うございますが、浜田様、お泊りになりますか?」
「あ……もうこんな時間か……。うーん、連絡もしてないからな、ちょっと電話借りますね」
「はい」
浜田君が立ち去ると、テーブルに並べていた写真が床に落ちた。
ジェーンさんは、こういうとき書類の中身も見て見ぬふりをしてくれる。けれど今回は違った。
絨毯の上に落ちた写真を拾い上げた、彼女の顔が凍りついた。
ああそうか、人造人間なのだから、何かを知っているのかもしれない。それは僕もぼんやりと考えていたことで、ジェーンさんにも尋ねてみようかと思っていたところだった。
「舞人様、彼は、」
「うん、ちょっとね。なんでも人造人間らしいけど、」
「教えてください!」
「えっ……」
追いすがるように僕の腕を掴んだジェーンさんは、まさしく必死の形相だった。
「教えてください、彼は、ユリウスは、どこにいるんですか!」
「ちょ、ちょっと待って、」
「舞人様、お願いです、どうか、」
わけがわからなかった。
僕が彼のことを聞こうとしているのに、どうして逆に問いただされているんだろう。一つだけわかったのは、切羽詰った顔をしているジェーンさんにとって、ユリウスというこの人造人間が、とても大切な存在だということだ。
いつの間にか雨が降り出したようだ。庭の噴水に降り注ぐ音は、僕の意識を過去へと呼び戻すようだった。